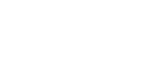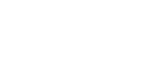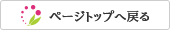ページの本文です。
教員紹介
2024年7月1日更新
文化情報工学科
| 伊藤さとみ 研究室案内 研究者情報 |
言語情報学、言語学 |
| 言語の意味と音声の関係を研究しています。同じ言葉でも違うイントネーションで話されると、誉め言葉が嫌味になったり、けなす言葉が親しみを表したりすることを日常に経験することは多いと思います。私の研究室では、Praatなどのソフトウェアを使って音声を可視化し、その特徴を抽出してデータサイエンスの手法で分析することにより、イントネーションが言葉の意味をどのように変えてしまうのかを研究しています。 | |
| 伊藤貴之 研究室案内 研究室HP |
マルチメディア、 コンピュータビジョン |
| データサイエンスのコア技術のひとつとして、データを効果的に画面表示する情報可視化の研究に取り組み、幅広い分野や幅広い産業のデータを情報可視化によって分析しています。共創工学部が対象とする言語・地理・人間環境などのデータも可視化してみたいと考えています。その他の研究として、マルチメディアやコンピュータビジョンの諸技術を活用することで、音楽や絵画の分析や理解にも取り組んでいます。 | |
| 宮澤 仁 研究室案内 研究室HP |
地理情報学、人文地理学 |
| 地理情報は、地球上の諸事象について位置を示す情報とそれに関連付けられた情報のことです。デジタル化が進んだ現在では地理情報システム(GIS)がその統合的処理を担っており、学際的研究の共通基盤から社会の情報インフラまで多岐にわたって活用されています。人文学・社会科学分野の地理情報の可視化や空間分析から地域の文化的・社会的課題を明らかにするとともに、共創工学の趣旨から持続可能な地域、豊かな文化に囲まれた地域をデザインするためのプラットフォームとしてGISを応用します。 | |
| 坂田綾香 研究者情報 |
統計科学、情報科学 |
| 統計学や機械学習、情報科学の問題を、統計物理学で使われる数学的手法を用いて研究しています。特に、学習アルゴリズムの性能や収束性などを理解することを目指しています。また、スピングラス理論やランダム行列理論などの手法を応用し、高次元における推論や学習の基本原理に迫ることにも取り組んでいます。さらに、生物学や神経科学の現象と機械学習の接点に着目し、ネットワーク構造や動力学の観点から情報処理の本質を探る研究も進めています。 | |
| 埋忠美沙 研究者情報 |
文化情報学、演劇学 |
| 日本演劇、歌舞伎を研究しています。形に残らない演劇を研究するためには台本や劇評といった文字資料のみならず、浮世絵・ブロマイドといった図像資料や映像・音声といった視聴覚資料など、多様な資料を複合的に扱うことが必要ですが、デジタルアーカイブの構築によって、近年その手法は拡大しつつあります。文系の手法をベースにデータサイエンスを用いることで、多角的なアプローチによる演劇研究に取り組みたいと考えています。 | |
| 土山 玄 研究室案内 研究室HP |
テキストアナリティクス、 情報学フロンティア、統計学 |
| 文体には個性があらわれると考えられています。日本語の文章では、特に助詞や助動詞、句読点などの用法に書き手の習慣的かつ形式的な特徴があらわれます。そこで、『源氏物語』などの古典作品や夏目漱石の小説といった多様な文学作品のテキストデータを対象とし、データサイエンスの手法を用い、文体的特徴の出現傾向を分析することで作者の識別・同定や文献の成立過程の推定を試みるという文理融合の研究を行っています。 | |
| Le Hieu Hanh 研究室案内 研究室HP |
データベース、データ工学 |
| 多種大量なデータを蓄積し有効に活用することが求められる中、信頼性の高いデータ格納方法や高速なデータ処理および高度なデータ分析等を実現するために、データ管理活用に関する研究を行っています。その中、医療・言語・地理・文化等といった多種多様な情報を対象とし、データを有効的に集積・格納した上で、有益な情報を創出する分析方法の研究開発を取り組んでいます。 | |
| 土田修平 研究室案内 研究室HP |
人間情報学、システムデザイン、 ヒューマンインタフェース・インタラクション |
| 工学的なアプローチにより未知の表現世界を探求する「表現工学」の研究に取り組みます。動きや感覚をデータ化し、情報として処理することで、新たな表現やそれを支援する手法の創出を目指しています。具体的には、アート・エンタテインメントやダンスなどの分析・創作・指導・評価などへ応用していきます。 | |
| 遠藤みどり 研究室案内 研究者情報 |
歴史情報学、日本史学 |
| 歴史学は、残された過去の記録(歴史資料)を客観的に分析し、当該期の歴史像を構築する学問です。近年は歴史資料をデジタル化したり、デジタル化した史料を利用したりすることで、従来の人的作業ではできなかった長期的・網羅的分析が可能となってきました。そのなかで日本の古代社会について、より客観的で具体的な分析を行うため、律令官僚人事データベースの構築と、その分析手法の確立に取り組んでいます。 | |
| 佐藤有理 研究室案内 研究室HP |
思想情報学、認知科学 |
| 人間とAIモデルのパフォーマンス比較を通して人間の様々な認識の不思議にせまる研究をしています。論理学、分析哲学、言語科学、実験心理学、認知神経科学、人工知能など文理を横断する認知科学の学際的手法をとっています。とくに言葉や画像の意味理解に注目していて、統計・機械学習だけでなく論理のシンボリックなアプローチも重視しています。 | |
共創工学部学部長インタビュー、教員紹介掲載
 学報—OCHADAI GAZETTE—2023年7月号 (新しいウインドウが開きます)
学報—OCHADAI GAZETTE—2023年7月号 (新しいウインドウが開きます)