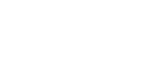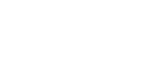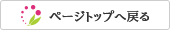ページの本文です。
推薦図書コーナー
2024年12月2日更新
推薦図書コーナー
一教員一冊で、各自の分野それぞれの魅力が伝わるような本を選びました。高校の教科・科目では扱われない分野が多く、イメージを持ちにくいと思いますので、その参考になればと企画しました。
言語学
『よくわかる言語学』窪園晴夫編(著), ミネルヴァ書房
この本では、言語学の様々な分野のトピックが、それぞれ見開き一ページで紹介されています。ですから、ぱらぱらめくって面白いと思ったところから読み始めることができます。言語学は高校では教えないため、実態がよくわからない人も多いと思いますが、多岐にわたるこの学問の面白さを、この本で体験してみてください。【伊藤さとみ】
https://www.minervashobo.co.jp/book/b472725.html(新しいウインドウが開きます)
情報可視化
『データ視覚化の人類史―グラフの発明から時間と空間の可視化まで』マイケル・フレンドリー/ハワード・ウェイナー(著)/飯嶋貴子(訳), 青土社
折れ線グラフや棒グラフをはじめとするデータ視覚表現はどのように生まれたのか、ナポレオンやナイチンゲールといった歴史上の偉人のエピソードとともに紹介する書籍です。データサイエンスの最重要なプロセスの一つでもある「可視化」「視覚化」の考え方を、その歴史とともに理解できる一冊となっています。【伊藤貴之】
https://seidosha.co.jp/book/index.php?id=3626(新しいウインドウが開きます)
地理情報学
『やさしく知りたい先端科学シリーズ8 GIS 地理情報システム』矢野桂司(著), 創元社
現在、さまざまな分野でGIS(地理情報システム)の活用が進んでいます。文化情報工学科では、GISを専門的に学ぶことができます。本書では、GISの起源からSociety 5.0におけるGISの活用まで、65の項目についてわかりやすく解説しています。GISの基礎は高校の地理で学ぶ内容でもあるため、高校生の参考書としても適しています。【宮澤仁】
https://www.sogensha.co.jp/productlist/detail?id=4258(新しいウインドウが開きます)
文化情報学
『文化情報学ガイドブック』赤間亮/鈴木圭子/八村広三郎/矢野桂司/湯浅俊彦(編), 勉誠出版
情報技術を用いた文化研究の手法を、伝統芸能、美術、地理、図書館学など、さまざまな分野の研究者が具体的に紹介しています。「文理が融合した研究とは何?」を知るための、おすすめの一冊です。【埋忠美沙】
https://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=100405(新しいウインドウが開きます)
歴史情報学
『歴史情報学の教科書 歴史のデータが世界をひらく』後藤真/橋本雄太(編), 文学通信
これまでの歴史学に、情報学の知見を組み合わせるとどんな新しいことができるのか?歴史情報学という新たな分野の現在と未来について、さまざまな視点からわかりやすく解説されています。【遠藤みどり】
https://bungaku-report.com/metaresource.html(新しいウインドウが開きます)
ヒューマンコンピュータインタラクション
『新しいヒューマンコンピュータインタラクションの教科書 : 基礎から実践まで』玉城絵美(著), 講談社
ヒューマンコンピュータインタラクション(HCI)の分野を基礎から実践まで広く網羅した教科書です。技術的な背景を持たない方にも配慮されており、カラフルでわかりやすい図が多く取り入れられています。HCIに初めて触れる方にオススメです。【土田修平】
https://www.kspub.co.jp/book/detail/5302637.html(新しいウインドウが開きます)
認知科学
『はじめての認知科学 (日本認知科学会監修「認知科学のススメ」シリーズ1)』内村直之/植田一博/今井むつみ/川合伸幸/嶋田総太郎/橋田浩一(著), 新曜社
認知科学 (Cognitive Science) は、「人間とAIを比較して人間を理解する」ことを1950年代頃から行ってきた分野です。人文・社会科学、情報学、工学、生物学の垣根を越えた学際的分野でもあります。なぜそんな(面倒そうな)アプローチをとるのか、認知科学の戦略や考え方に触れられる格好の入門書です。【佐藤有理】
https://www.shin-yo-sha.co.jp/book/b455541.html(新しいウインドウが開きます)
テキストアナリティクス
『この本を書いたの誰だ? 統計で探る"文章の指紋"』村上征勝(著), 勉誠出版
実例に基づいて、書き手が明確ではない文章の書き手を統計的に推定する方法を解説した書籍です。また、この分野がどのように発展してきたのかも分かりやすくまとめられています。【土山玄】
https://bensei.jp/index.php?main_page=product_book_info&products_id=101116(新しいウインドウが開きます)
統計科学
『自己組織化と進化の論理: 宇宙を貫く複雑系の法則』 スチュアート・カウフマン(著)/米沢 富美子(翻訳), 筑摩書房
生命から経済、宇宙まで、あらゆるスケールに現れる「自発的秩序」を、複雑系科学の視点から解説しています。特に、統計物理学の数理モデルを手がかりに生命進化の定量的描像に迫る過程は、分野横断型研究の醍醐味を伝えます。高校までバラバラだった知識が一つに繋がる面白さをぜひ体験してください。【坂田綾香】
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480091246/(新しいウインドウが開きます)
データベース
『図解まるわかり データベースの仕組み』坂上幸大(著), 翔泳社
現代社会では、コンピュータとインターネットの普及により、膨大な情報が日々生成されています。それでは、この情報はどこに、どのように保存され、管理されているのでしょうか?本書では、情報の保管や管理を担う「データベースシステム」の基礎知識をはじめ、操作方法、設計、運用までを、多くの図解を交えながら分かりやすく解説します。【Le Hieu Hanh】
https://www.shoeisha.co.jp/book/detail/9784798166056(新しいウインドウが開きます)